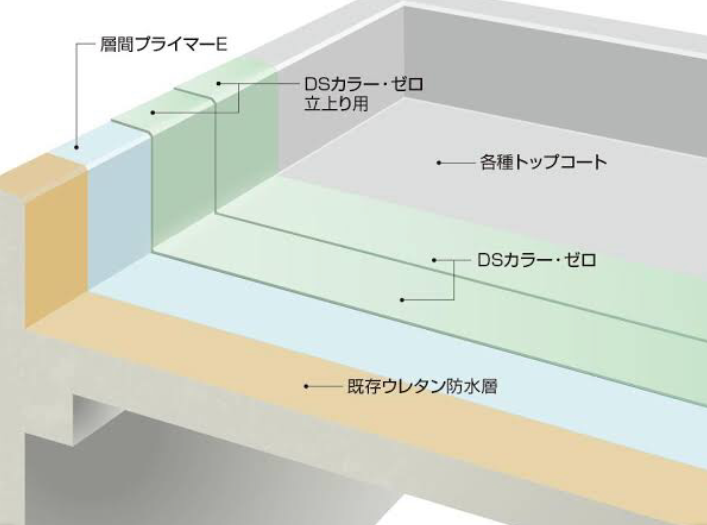屋根・ベランダの笠木交換にかかる費用と施工方法を解説
2024/10/16
屋根・ベランダ・バルコニーなどの上部に取り付けられている仕上げ材が「笠木(かさぎ)」と呼ばれるものです。 普段あまり気にする場所ではないかもしれませんが、笠木は建物の外壁や躯体を保護する大切な役割を持っています。
本記事では、笠木交換の必要性や費用の目安、施工方法などについてわかりやすく解説します。 また、施工業者の選び方についても紹介しますので、笠木交換の参考として、ぜひ内容をチェックしてみてください。
笠木交換の必要性とは?
なぜ笠木は定期的に交換しなくてはならないのでしょうか。
「今までまったく気にしていなかった」という方もいらっしゃいますよね。
交換を行わなくてはならないのは、次のような理由があるためです。
- 剥がれや飛散などにつながるリスクがあるため
- 外壁材や躯体の腐食を引き起こすおそれがあるため
- 雨漏りを引き起こすリスクがあるため
笠木はビスや釘などによって固定されている状態ですが、劣化すると剥がれや飛散などのリスクがあります。
また、外壁や躯体の腐食にもつながってしまうでしょう。
さらに、笠木の劣化は雨漏りを引き起こす可能性もあるため、注意しなくてはなりません。
建物を守るためにも、劣化が進んでしまう前に補修・交換を行いましょう。
笠木の種類と選び方
笠木の材質の代表的な種類は以下のとおりです。
- 木製
- 金属製(鉄・アルミニウム・ステンレスなど)
- 石製
- セメント製(コンクリート・モルタルなど)
笠木の材質は、使う場所に合わせて選ぶ方法が一般的です。
住宅の階段や対面キッチンなどの場所には、手触りのよい木製の笠木が使われています。
屋外で使われることが多いのは、耐久性の高いアルミやステンレスなどの金属です。
塀・屋上などでは石製やセメント製の笠木が使われる場合もあります。
劣化時に補修と交換のどちらにするかは、使われている材質次第です。鉄製なら劣化しても「笠木カバー」によって補修できます。
しかし、アルミニウムのように厚い笠木は交換工事が必要です。
笠木交換にかかる費用の目安
笠木交換にあたって、費用が気になる方も多いのではないでしょうか。
費用は必要な工事の内容や、使われている材質などの要素によって変わってきます。
一般的な費用の目安は以下のとおりです。
- 笠木交換にかかる費用の目安…10,000円~/平方メートル
- 笠木カバーにかかる費用の目安…5,000円~/平方メートル
外壁が腐食している状態なら、別途費用が必要になるでしょう。
どのくらいかかるかは、業者に見積もりを依頼して確認する方法が確実です。
笠木の補修方法
笠木には3つの補修方法があります。
- コーキング補修
- 笠木交換
- 笠木カバー
必要な補修方法は笠木の状況・劣化の程度・使われている素材などの要素で違ってきます。
費用も変わりますので、どの方法になるのか業者に確認してみるのがおすすめです。
3つの方法について、それぞれどのようなものか内容を見ていきましょう。
コーキング補修
コーキングに亀裂が入っていたり、隙間ができていたりする場合に行われるのが、コーキング補修です。
ごく軽度の劣化なら、コーキング補修だけで済む場合もあるでしょう。
笠木交換
笠木交換とは、既存の笠木を撤去して新しく設置する方法です。
腐食や雨漏りが深刻な状況であれば、下地の交換も必要になります。
笠木カバー
笠木カバーとは、既存の笠木をガルバリウム鋼板で覆う方法です。
軽度の劣化ならば笠木カバーで対応できます。
ただし、笠木カバーは鉄製の笠木に使える方法です。
アルミニウムは厚いため、交換が必要になります。
笠木交換の施工手順と注意点
笠木交換を行うなら手順を知っておきましょう。
基本的な笠木交換・笠木カバーの手順をそれぞれ簡単に紹介していきます。
どのような手順で進められるのか、ぜひチェックしてみてください。
笠木交換の施行手順
笠木交換は次のような手順で進められます。順番に見ていきましょう。
①既存の笠木の撤去と解体
最初に行われるのが既存の笠木の撤去と解体です。
劣化の度合いによっては、笠木の板金と下地のみの解体で済む場合があるでしょう。
②下地の調整
笠木を撤去・解体が終わったら、劣化の程度に合わせて下地を調整して木材を取り替えます。
劣化の状況によっては躯体や外壁の交換なども必要です。
躯体や外壁の劣化度合いは、外側から見ただけではわかりません。
どの程度劣化しているのか、専門の業者に確認してもらいましょう。
③ルーフィングシートの張り付け
下地を調整したら、ルーフィングシートの張り付けが行われます。
ルーフィングシートを張りつけるのは、防水効果を高めるためです。
ベランダやバルコニーなど雨水が入り込みやすい場所は、特に注意する必要があります。
④笠木の加工と配置
下地の形状に合わせて加工した笠木を配置します。
雨水が排出されるよう、微調整が必要です。
⑤シーリング材の充填
笠木板金を配置したら、継ぎ目の部分に「捨てシーリング」を行います。
表面から見えない場所に、防水を目的として行うのが捨てシーリングの処理です。
捨てシーリングをしておくことにより、内部への水の浸入を防げます。
⑥笠木の固定
捨てシーリングの処理が終わったら、ビスで笠木を固定していきます。
以前は笠木の固定には釘が使われていました。
しかし、近年はサビが出にくいステンレスのビスを使う方法が一般的です。
⑦養生
防水処理で使うシーリング材がはみ出ないよう、ビスの周囲に養生を行います。
⑧シーリング材による防水処理
ビスの部分には防水処理を行わなくてはなりません。
シーリング材を充填して平らにします。
⑨最終確認
シーリング材を充填したら、養生を剥がして全体の確認を行います。
笠木カバーの施行手順
笠木カバーは以下の手順で進められます。
①下地の調整
既存の笠木はそのままの状態で、まずはシーリングを施します。
下地に劣化が見られる場合は、下地材の調整が必要です。
②防水処理
防水のためにルーフィングシートの張りつけを行います。
また、継ぎ目にも防水処理が必要です。
③笠木の設置とシーリングの充填
新しい笠木を設置したらシーリングを充填します。
笠木の劣化原因と交換のタイミング
笠木の劣化が起きる原因はさまざまです。
劣化する代表的な原因と、交換のタイミングについても見ていきましょう。
笠木の劣化原因
笠木が劣化する主な原因として挙げられるのは、次の3つです。
- 雨水
- 紫外線
- 自然災害
笠木の劣化を引き起こすおもな原因となっているのが雨水や紫外線です。
外観からはわかりませんが、雨水や紫外線で少しずつ笠木が劣化していきます。
地震・大雨・台風なども笠木の劣化を引き起こす原因です。
笠木の劣化を放置していると次のような症状を引き起こすため、補修しなくてはなりません。
- 下地の腐食
- シロアリの発生
- 外壁材の浮きや剥がれ
- 雨漏り
下地が腐食すると、シロアリの発生や外壁材の浮き・剥がれといった症状へとつながってしまいます。
笠木の劣化が原因で雨漏りが起き、建物内部を傷めてしまうこともあるでしょう。
■笠木を交換するタイミング
建物を守るためには定期的な笠木の補修や交換を行わなければなりません。
そこで、補修や交換のタイミングについても把握しておきましょう。
隙間に使われているシーリング材は、およそ5年が一般的な寿命です。
5年が過ぎたら、シーリング材の充填を検討してください。
笠木は25年が交換を実施するタイミングです。
ただし、劣化が進んでいるようであれば、25年経っていなくても交換しなくてはなりません。
劣化していると思われる症状が出ている場合はそのまま放置せず、なるべく早めに専門の業者へと相談してみてください。
笠木交換の施工業者の選び方
笠木交換にあたって、施工業者の選び方がわからず悩む方も多いでしょう。
施工業者の選び方でのポイントは次の3つです。
- 見積もりの内容
- アフターフォローの有無
- 対応のよさ
3つのポイントについて解説します。
見積もりの内容
笠木交換では、まず業者に見積もりを依頼しましょう。
複数の業者に見積もりを依頼すると、比較検討する際に役立ちます。
価格だけでなく、見積もりの内容が明確であるかもチェックしてみてください。
見積もりの内容が「一式」になっている場合は、内訳を確認する必要があります。
内容を確認しても教えてくれない業者は避けましょう。
アフターフォローの有無
笠木交換を依頼する上で、アフターフォローサービスの内容を契約書や説明資料で確認することが大切です。
アフターフォローがあると言われただけでは不十分で、具体的なサービス内容が文書で記載されているかどうかを確認しましょう。
施行後の無償保証期間や定期点検サービスなどが記載されていることが望ましいでしょう。
対応の良さ
施工業者の選び方では、対応の良さも重視したいポイントのひとつです。
対応の良い業者であれば、施工にあたってわからないことがあっても気軽に相談できます。
特に注意しなければならないのが、以下のような業者です。
- 訪問販売業者である
- 契約を急がせる
- 保証についての文章がない
特に訪問販売業者への依頼はトラブルに発展しがちですので、気をつけてください。
まとめ
- 笠木が劣化すると外壁の腐食や雨漏りなどを引き起こす恐れがある
- 笠木の材質にはさまざまな種類がある
- 笠木の材質は使う場所に合わせて選ぶ必要がある
- 笠木の補修には「コーキング補修」「笠木交換」「笠木カバー」という方法がある
- 笠木は雨水や紫外線、自然災害などの影響を受けて劣化してしまう
- 笠木交換のタイミングは25年が一般的な目安である
屋根・ベランダ・バルコニーといった場所に使われている仕上げ材が笠木です。
劣化した笠木を放置すると、外壁材の腐食や雨漏りなどにつながるため、注意しましょう。
定期的な補修や交換を行えば、建物が傷むのを防げます。
シーリング材の充填は5年、笠木の交換は25年で行うのが一般的なタイミングです。
業者選びで悩んでいるのであれば、見積もりの内容が適切でアフターフォローがある業者に相談しましょう。
笠木の補修や交換によって建物を腐食や雨漏りなどから守ってください。